(琉球新報2025年4月13日論壇)
四月十四日から科学技術週間がはじまる。また五月五日は子供の日だ。そこで「音と話ことばの“子供博物館”」を“設置”したので、案内しよう。
「子供博物館」は、「沖縄大百科事典」によれば「文化、科学などに関する子どもたちの興味や関心を高めるため、実験、実習、創作活動などの機能に重点を置いた社会教育施設」だった。1954年から1966年まで存続し、「沖縄少年会館」の設立により、その機能は移転された。
子供博物館は、久茂地小学校の近くの丘の上に建つビルで、1階より2階の方が大きく、いかにも宇宙をめざす研究所というような風ぼうをしていた。私は小学生のころその近くでよく遊んだものだ。
本紙の「ティータイム」に「鉄腕アトムの歌」について寄稿したら、「丘の上に建つ子供博物館」を、編集者が先を読んで「沖縄少年会館」に置き換えていた。テレビアニメ鉄腕アトムの初回は1963年で、少年会館はまだなかった。
1965年に私は那覇中学校1年生で、天文クラブに属していた。クラブ活動の一環として、子供博物館でプラネタリウムを観て、天体望遠鏡で惑星を観測した。プラネタリウムは、沖縄で唯一のもので、そのスクリーンはドームでなく組み立て式の巨大な傘だった。また天体望遠鏡は沖縄で最大の口径だった。月面と土星の輪を観測して、天文学者ガリレイが見て考えたことを追体験することができた。
子供博物館は、科学への夢を育む希望の博物館だった。私は、天文クラブを経て国費沖縄学生になり、琉球大学の教員になった。子供博物館は私たちにとって、小中学生のころにその後の人生を考えるための重要な施設だった。
前述の「ティータイム」で、科学に関して何らかの寄与をしたいと書いた。ホームページ「音・話ことばの実験室」は、もともと子供博物館と同様の趣旨で開設したものだ。そこでこれを「音と話ことばの子供博物館」とも呼ばれるものにしたいと思う。まず、以前に書いた中学生にも分かる音声実験のページを改めて読めるようにした。また中学生でも作ることができる「音声生成模型」に関する展示をした。そのほか、これまで研究してきた琉球語の音声合成システム、音声認識ロボット、不思議な音声の各デモなどを展示した。
この機会に、QRコードの「音・話ことばの実験室」を訪ねてみてはどうだろうか。むかし子供博物館に出かけて行った、60年以上前の科学少年少女の皆さんも、ぜひご覧いただきたい。
(琉球大学名誉教授 高良富夫 72歳)
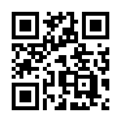
「科学への夢を育む実験室」は新聞社が付けた見出しです。
